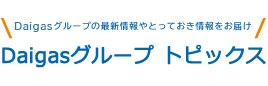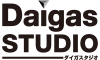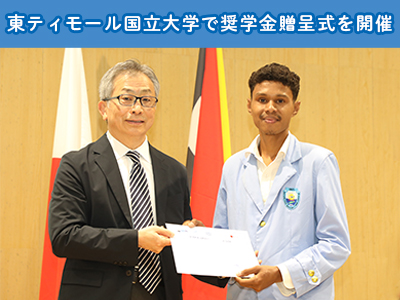大阪ガス硬式野球部 熱球道場「第12回 中継プレイで心がけること」

中継プレイが“ボールを繋ぐだけ”になっていませんか? このプレイの良し悪しが相手ランナーの進塁や失点を左右するので、中継プレイも重要な守備の1つ。
ただ繋ぐだけの中継にしないためには、内野手の動きが大切になってきます!
今回は、大阪ガス硬式野球部の名手のひとりである、近藤竜二選手に中継プレイで心がけることを聞きました。
次の3つのポイントを押さえれば、相手チームから脅威を持たれること間違いなし☆

■ポイント1 「位置取りと中継先までのラインを正確に把握すること」
近藤選手が一番心がけていることがこのポイント。外野手からの送球を正確につなぐために、内野手が投げる距離は少しでも短くするのがベストです。
要するに、その外野手が勢いのあるボールを投げられるギリギリの距離に立って返球を待つことが大切。
送球がシュート回転するなど、ボールの癖も頭に入れてくださいね!
外野手との距離感を把握するには、日頃の練習がものいいます。シートノックで外野手の癖をしっかりと把握しておきましょう。
外野手から「もっと後ろで待ってもらってもいいですよ」など、お互いのベストポイントが導き出せます(^^)
また、外野手と中継先とを結ぶラインを外さずに立つことも、送球をそらさない大切なポイントです。

■ポイント2 「どこへボールを投げるかによって捕球、送球の仕方を変える」
二塁送球時は浅く捕球 → クイックモーション、三塁送球やバックホームの場合は、自分のいい位置(胸あたり)でしっかり捕球 → その反動で自分の形をつくって送球、と投げ分けましょう。
ランナーが進塁を狙う姿を見ると、つい、焦ってクイックモーションで投げてしまいがちですが、全力送球の方が走者よりも速いので、慌てずしっかり捕球 → 全力送球をすることです。
日ごろのキャッチボールで、捕球、送球を鍛錬していることが大切となってきます!
■ポイント3 「試合前には、球場の広さや形をしっかり頭に入れておくこと」
例えば、東京ドームだと打者を二塁で刺せたとしても、京セラドームだと3ベースヒットになるなんていうこともしばしば。
それは外野からフェンスまでの距離の違いや、両翼からセンターへ向けての形状が球場ごとに違うからなんです。グランドに入ったら、まず、そこをチェックすること忘れずに。
中継プレイに入っても、実際にカットしない方がいい場合があります。
その判断基準は「返球が自分の両手を広げた範囲を超えてしまいそうならカットし、勢いあるボールがコース内に返球されてきたならカットしない」ことです!
最後に、近藤選手の今季の抱負を聞きました♪
「12年間培ってきた経験をいかして、今年こそはチームを日本一に導きます。皆さま、期待してください。」
野球のコツやヒントが満載。これまでの熱球道場も一緒にチェックしてみてくださいね♪
第1回「トンネルしない捕球法」
第2回「会心のホームランを打つには」
第3回「ストライクをバンバン投げたい!」
第4回「鉄壁守備を誇れる外野手になる!」
第5回「上手い走塁方法」
第6回「コントロールがよくなる投球術」
第7回「バントを決めるコツ」
第8回「三塁コーチャーの役割」
第9回「コリジョンルール導入で変わったこと」
第10回「先発ピッチャーの調整方法」
第11回「クイックモーションを修得するコツ」
大阪ガス硬式野球部のWebサイトでは、選手紹介のほか、各大会への出場予定や結果を掲載しています! ぜひご覧くださいね♪
大阪ガス硬式野球部のWebサイトはこちら
関連する記事
- 「社会貢献・文化・スポーツ」テーマの記事