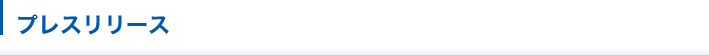
![]()
2018年7月20日
伏見酒造組合
大阪ガス株式会社
伏見酒造組合(理事長:増田 兵衞)と大阪ガス株式会社(社長:本荘武宏 以下、大阪ガス)は、大阪ガス独自の画像認識技術を活用して、日本酒の大吟醸酒造りに用いられる高度精白米*1の新たな評価手法を開発しました。両者は全国の酒造会社での新手法活用を推進することで、日本酒全体の品質向上に貢献していきます。なお、2018年9月に開催される「第42回酒米懇談会」(主催:酒米研究会)で、技術の詳細を共同発表する予定です。 兵衞)と大阪ガス株式会社(社長:本荘武宏 以下、大阪ガス)は、大阪ガス独自の画像認識技術を活用して、日本酒の大吟醸酒造りに用いられる高度精白米*1の新たな評価手法を開発しました。両者は全国の酒造会社での新手法活用を推進することで、日本酒全体の品質向上に貢献していきます。なお、2018年9月に開催される「第42回酒米懇談会」(主催:酒米研究会)で、技術の詳細を共同発表する予定です。 |
|||||
| 伏見酒造組合傘下の酒造会社の技術者で構成する伏見醸友会と大阪ガスは、2016年に新たな評価手法の開発に向けた取り組みを開始しました。大阪ガスが独自開発した、吸水による米の外観の変化を画像認識する技術を用いて、高度精白米の吸水性や形状の変化を定量的に観察すると共に、既定の酒米分析法による吸水性評価との比較、酒造現場のデータとの整合性を確認するなど評価手法として実用できるかどうかを検証しました。2年間の検証を経て、独自手法と規定手法に互換性があること、独自手法では規定手法で得られる情報に加え、吸水状況の可視化、吸水初期の水分量変化の計測が可能なこと、現場の感覚とよく一致していることが確認できました。 | |||||
| 近年、吟醸酒や大吟醸酒の需要が高まっており、全国の酒造会社が商品化に力を入れています。大吟醸酒造りでは、香りが高く淡麗な味わいに仕上げるため米の中心部だけを残した高度精白米を用いますが、洗米・浸漬工程において水を吸うスピードが速く、作業条件を判断する上で吸水特性が非常に重要な指標となります。この工程での水分量は、蒸米、麹づくりなど以降の工程での仕上がりに大きな影響を与え、ひいては酒の出来栄えを左右します。*2今回開発した客観的な評価手法の活用により、特に精緻な判断や操作が求められる大吟醸酒の高品質化が期待できます。酒造り職人である杜氏や蔵人が減少傾向にある中で、科学技術による技能伝承の支援にもつながる成果となりました。 | |||||
| 今後、伏見酒造組合と大阪ガスは、新手法を酒造りに活用するとともに、酒米の育種や栽培への活用、さらには新たな評価手法の開発など、引き続き共同で取り組みを進め、高品質な日本酒造りへの支援に努めていきます。 | |||||
|
|||||
| ▲ページトップ | |||||
| 伏見酒造組合:1875(明治8)年に設けた、「伏見酒造家集会所」が起源となり、1894(明治27)年「伏見酒造組合」へと改称。1909(明治42)年には伏見酒造組合醸造研究所を設け、科学技術導入により高品質の酒造りを推進してきた。明治期からは鉄道網の進展を力に、組合傘下の各蔵元が東京をはじめ全国への市場拡大に取り組んだ。現在、酒造会社23社、1組合が加盟している。 伏見酒造組合HP: http://www.fushimi.or.jp/ |
|||||
| 伏見醸友会:伏見酒造組合傘下の酒造会社の技術者で構成する団体で、1913(大正2)年に創立。 経験と勘をもとにした酒造りに科学的な知識や手法を導入するなど、日本酒の品質向上のための研究に取り組んできた。現在、<「技」を究める・「水」を守る・「米」を育てる>を3本柱として活動。醸造法の実態調査、地下水の保存と調査研究、共同研究による酒米の研究などの活動を継続し、酒造技術向上への貢献により日本酒産業の発展に努めている。 伏見醸友会HP: http://www.fushimi.or.jp/joyukai/ |
|||||
| 大阪ガス株式会社:エネルギー技術研究所内に「フード・サイエンス・ラボラトリー」(通称:食ラボ)を設置。食品加工・調理でキーとなる食材の変化を伝熱や構造解析技術を駆使して解明するとともに、得た知見から新たな食品分析技術の開発や食品加工・調理の制御に応用展開することで食材の特性の最大化に取り組んでいる。これまでに、賀茂ナスなどの野菜の健康調理法の開発や炊飯機器の開発支援などの研究成果がある。 フード・サイエンス・ラボラトリーHP: https://www.osakagas.co.jp/company/efforts/rd/labo/index.html |
|||||
| 以上 | |||||
|
|||||
|
|||||
プレスリリースの内容に関するお問い合わせや取材等のお申し込みは、リリースに記載のお問い合わせ先、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。