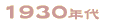
海外旅行など夢のまた夢であった戦前の日本。当時、ヨーロッパ映画は円熟した文化を垣間見られる唯一の“窓”だった。ガスビル講演場で催された映画鑑賞会にはこんな作品が…。
ジュリアン・デュヴィヴィエ監督の『モンパルナスの夜』(1933)。戦前の人気俳優アリ・ボール扮するメグレ警視が活躍する刑事映画の佳作だ。カナダの雄大な自然を背景にフランス系カナダ人の生活を描いた『白き処女地』(1934)もこの監督の手によるもの。ジャン・ギャバンの初主演映画で、彼はこれを機にスター街道をばく進していく。
1930年代はフランス映画の黄金期。デュヴィヴィエは、『ミモザ館』(1935)のジャック・フェデー、『巴里祭』(1932)のルネ・クレール、『どん底』(1936)のジャン・ルノワールと並ぶ四大巨匠の1人と評され、とりわけ日本で人気が高かった。ルナールの小説を映画化した『にんじん』(1932)、ギャバンの渋い演技が光る『望郷』(1937)など印象深い作品が多い。
鑑賞会では、ほかにも戦前のドイツ映画界を担ったグスタフ・ウチツキー監督の『ジャン・ダーク』(1934)、ウィーンの社交界を舞台にしたオーストリア映画『郷愁』(1935)などの名作も銀幕に映し出された。


