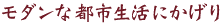
昭和6年(1931)満州事変、昭和12年には日中戦争が起こり日の丸弁当が奨励されます。時局という言葉が使われ戦意高揚がはかられました。
昭和13年国家総動員法施行。やがて昭和16年12月8日太平洋戦争が勃発し、「欲しがりません勝つまでは」がスローガンになります。
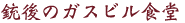
昭和14年(1939)、日中戦争下に興亜奉公日が決められ、毎月国民生活規制、戦意高揚がはかられました。ガスビル食堂やガスビル喫茶も自粛営業を行いました。
翌昭和15年には、奢侈品等製造販売制限規則が施行され、食堂では昼食は2円50銭、夕食は5円、一品料理は一品1円を越えるものは販売できなくなり、米食の提供が禁止されました。


